こんにちは、ToMO(@tomo2011_08)です。
退職金は、会社を辞めた後の老後の生活を支えてくれる大事なお金です。
そのため、できるだけ自分にとって最適な方法で受け取り、税金を少なく、手取りを多く受け取りたいものです。
以前に、退職金にかかる税金や、最適な受け取り方法などについて以下の記事で解説しました。
当記事を読まれる前に、以下の記事で現在の退職金課税制度を理解しておくことをおすすめします。
しかし、2025年3月5日の衆院予算委員会で、石破首相から退職金課税制度は「見直すべき」という言及がありました。
一部のメディアでは、「サラリーマン増税」や「就職氷河期世代を馬鹿にしている」、「どれだけ搾り取るんだ」といった国民の声の報道もありました。
増税に関しては、「財務省解体デモ」が起こるほど国民の経済的な余裕はなくなっており、怒りは大きくなっています。
最近においても、高額医療費制度の制度改正(増税)において国会が大紛糾したばかりです。
高額医療費制度については、以下の記事で書いています。
国の収入は過去最高を更新し続けているのに、政府と財務省は手を変え品を変えて増税を進めており、国民の不満は募るばかりです。
とはいえ、不満ばかり言っていても何も変わらないので、まずは一体どういった退職金課税制度の増税内容で、いつから開始しようとしているのか、しっかり理解して備えることが大事でしょう。
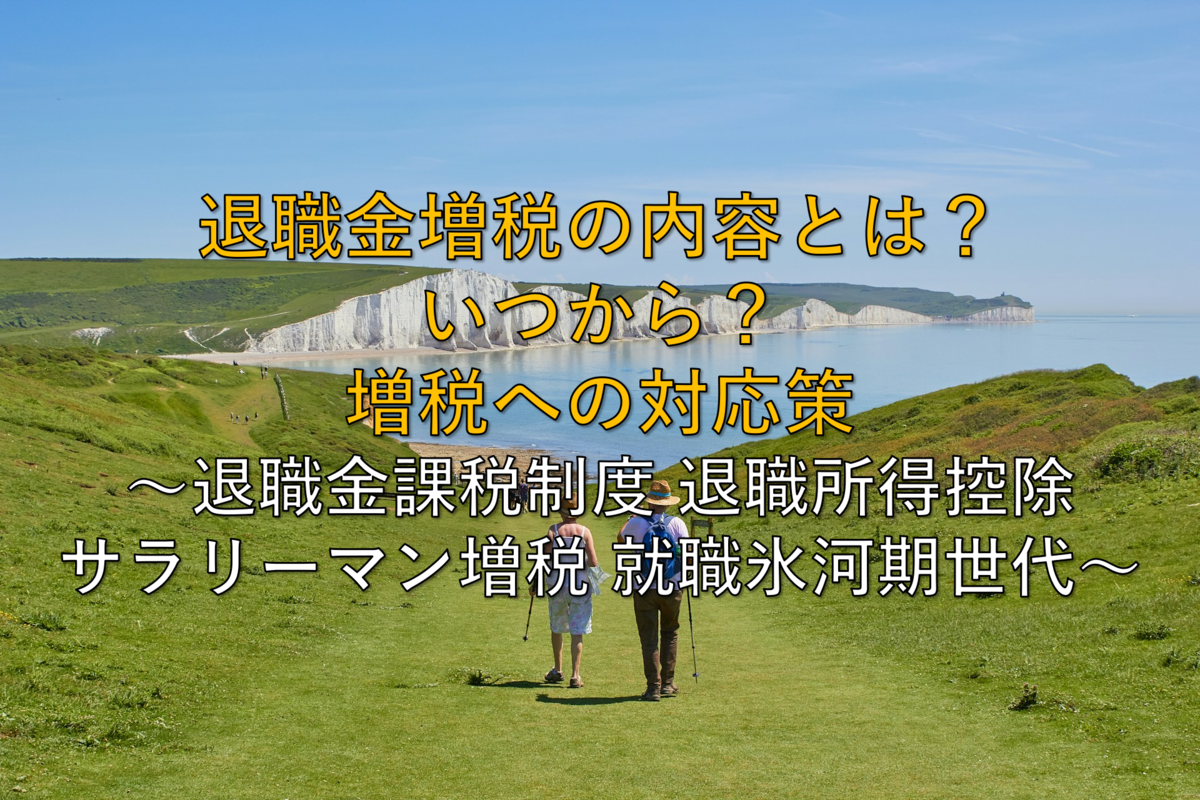
そこでここでは、退職金の税制改正の方向性や、いつから開始されるのか、退職金増税の対応策についてご紹介します。
サラリーマンの方で今後退職金を受け取られる方におすすめの記事になります。
目次
退職金の税制改正の方向性
現行制度では、勤続年数が20年までは1年につき40万円、20年以降になると1年につき70万円が退職金から控除され、同じ会社に長く在籍していた社員の方が優遇される制度設計となっています。
この仕組みは終身雇用が主流だった1989年(平成元年)から30年以上続いており、転職が主流となっている現代の働き方にはそぐわないなどとして税制調査会などでも見直しが提言されていました。
例えば同じ会社に40年働いていた人と、20年ずつ別の会社で働いた人の退職金を比較した場合、現行制度では課税の重さは異なり、転職者が損になってしまいます。
それを転職が主流となっている現代の働き方に合わせ中立にするということです。
具体的な改正内容はまだこれから検討ということですが、改正の方向性としては、以下となっています。
- 公平な税負担の実現
現在、退職金は「退職所得控除」などの税制優遇が手厚く、一時的な高額所得であっても税負担が軽減される仕組みになっています。
この優遇措置が、他の所得と比べて「優遇されすぎている」との意見があります。
- 多様な働き方への対応
近年の副業やフリーランスの増加により、退職金を受け取らない働き方を選ぶ人も増えています。
このような状況の中で、退職金制度だけを優遇する仕組みを見直す動きが進んでいます。
- 税収増加の必要性
少子高齢化による社会保障費の増大や、コロナ禍以降の財政赤字の補填のため、税収を増やす政策の一環として退職金優遇の見直しが検討されています。
増税の可能性が高い内容
- 長期勤務者への優遇措置縮小
勤務年数が20年以上の人に対して退職所得控除が縮小される方向で議論されています。
- 退職金の分割受け取りにも増税の影響
年金形式で受け取る退職金に対しても税負担が増える可能性が指摘されています。
実施時期はいつ?
2023年末の税制改正大綱で検討が進められており、早ければ2025年度からの施行が想定されていました。
ただし、具体的な法案成立時期や詳細な施行時期については、国会の動向次第で変更される可能性があります。
2025年3月の国会では審議が先送りとなり、秋の国会であらためて審議するということですので、施行は2026年度以降となるでしょう。
退職金の増税内容は?
増税により、どのような変更が行われる可能性があるのか、具体的な内容を確認してみましょう。
退職所得控除の縮小
退職金の優遇税制である「退職所得控除」が見直される可能性があります。
現行の退職所得控除の仕組み
20年以下の勤務期間 40万円 × 勤続年数
20年を越える勤務期間 70万円 × (勤続年数 - 20年) + 800万円
見直しの方向性
勤続年数が長期の人(たとえば20年以上)の控除を縮小
一時金と年金形式の税制優遇の見直し
退職金を一時金形式で受け取る場合と、年金形式で分割して受け取る場合で適用される控除に変更が加えられる可能性があります。
- 一時金形式
退職所得控除の縮小や、課税対象額の計算方法変更が検討されています。
- 年金形式
公的年金等控除の見直しにより、年金受け取り額が一定を超えると税負担が増える可能性があります。
所得税率の引き上げ
退職所得に対する課税率そのものが見直される可能性もあります。
これにより、退職金の課税対象額が増えると、税負担が増大することが予想されます。
退職金増税の影響を最小限に抑える方法
増税が実施された場合でも、適切な対策を取ることで税負担を軽減できる可能性があります。
以下に具体的な節税方法を紹介します。
退職時期を調整する
増税施行前に退職すれば、現行の優遇措置が適用される可能性があります。
退職時期を検討する際は、会社の退職金規定や税制改正のスケジュールを確認しましょう。
退職金の受け取り方を工夫する
一時金形式で受け取る場合、退職所得控除を最大限活用できるよう、受け取る年を分ける方法を検討してください。
年金形式で受け取る場合、公的年金等控除を活用し、税負担を分散することが可能です。
転職や再雇用を活用する
転職や再雇用によって退職金の受け取りを分割することで、1回あたりの課税対象額を減らすことができます。
専門家に相談する
税理士やファイナンシャルプランナーに相談し、自分の退職金の受け取り方や時期を最適化することで、節税効果を最大化できます。
まとめ
今回は、今後検討が開始される退職金課税制度の改正について記事にしました。
まだ国会での審議がされていないので、改正の内容や、開始時期は不確定ではありますが、現行制度の退職金への税金から大きく増えるようなことになれば、退職後の生活や人生設計に影響は甚大です。
たしかに、同じ会社で勤続年数が20年以上の場合に税金が優遇されるのは、人材の流動化の観点で時代にそぐわないというのは理解はできます。
しかしながら、突然退職金の税金が増税されることは、特にもうすぐ定年退職される方にとっては納得できないでしょう。
2025年3月の国会では審議は先送りされ、秋の国会での審議が予定されています。
そのため、実施時期は2026年度以降となりそうです。
まだどのような改正になるか分かりませんが、氷河期世代の私としては、これまで時代のツケを押し付けされてきた氷河期世代にまた負担がかからないことを祈ります。
審議の行方については、引き続き注視して、近々退職される方は、できるだけ税金を最小化できるような対策を検討しましょう。
今回も最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
この記事がいいと思ったら、いいねやブックマーク、読者登録をよろしくお願いします。
最新の情報を発信していますので、X(Twitter)のフォローもよろしくお願いします。
